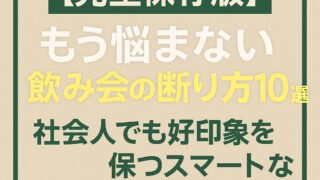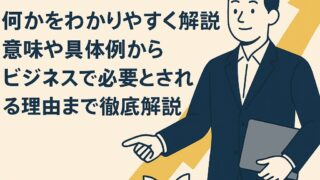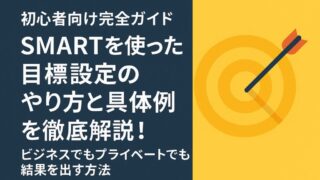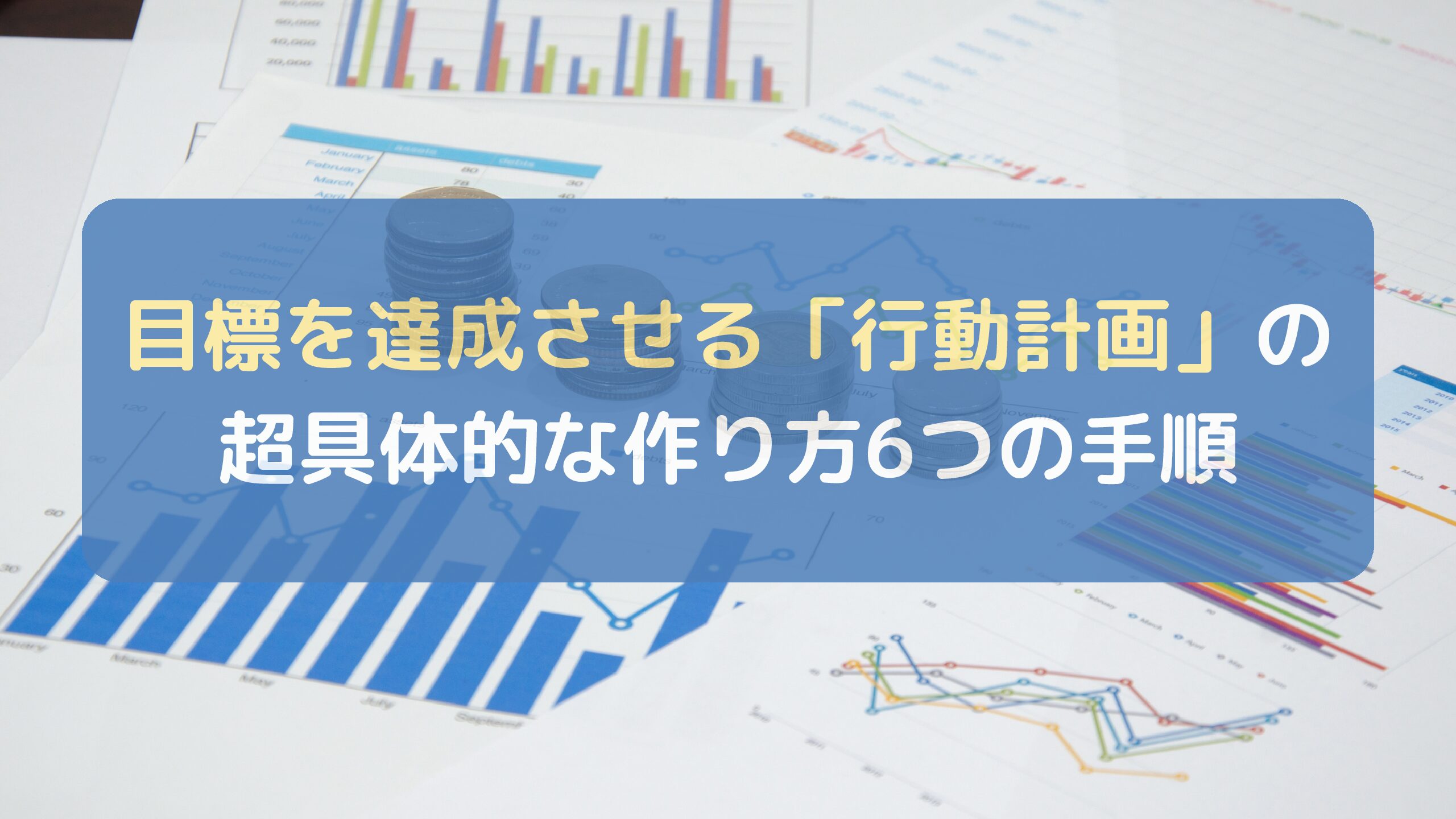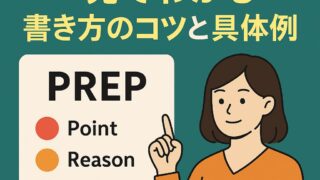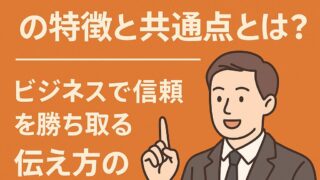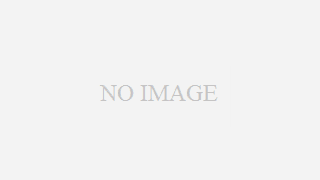仕事のストレスが増える日本の現状とは?
「最近、職場のストレスが限界」「疲れが取れないのに仕事は増える一方」——
こう感じている人は少なくありません。
厚生労働省が発表した2024年(令和6年)版「労働安全衛生調査」によると、
日本の労働者の68.3%が“仕事や職業生活に強いストレスを感じている”と回答しています。
これは実に3人に2人以上がストレスを抱えている計算です。
一方で、長時間労働者(残業80時間超)の割合は1.5%に減少。
つまり、「働きすぎ」だけが原因ではないストレス構造が日本社会に存在しているのです。
厚生労働省が定義する「仕事のストレス」とは?
ストレスという言葉はよく耳にしますが、厚生労働省はこれを次のように定義しています。
「ストレスとは、心身に負担がかかり、心理的・身体的・行動的に変化が現れる状態」
具体的には以下のような症状が代表的です。
● 身体面のストレス反応
- 頭痛・肩こり・腰痛
- 胃痛・食欲不振・下痢や便秘
- 動悸・息切れ・不眠症
● 行動面のストレス反応
- 飲酒・喫煙の増加
- 仕事上のミス・事故
- 人間関係トラブルの増加
これらが長期間続くと、うつ病や適応障害などのメンタル不調につながる恐れがあるため、早期の予防が重要です。
日本の職場で「仕事のストレス」が生まれる3大要因
労働安全衛生調査の結果によると、労働者が強いストレスを感じる要因トップ3は以下の通りです。
| 順位 | ストレス要因 | 割合(令和6年) |
|---|---|---|
| 1位 | 仕事の量 | 43.2% |
| 2位 | 仕事の失敗・責任の発生 | 36.2% |
| 3位 | 仕事の質 | 26.4% |
では、それぞれの背景をもう少し詳しく見てみましょう。
①「仕事の量」が多すぎる
最も多いストレス要因は、「仕事の量が多い」という声です。
しかもこの割合は前年より3.8ポイント増加。
人手不足が続く中で、一人ひとりの業務負担が増している現状があります。
法的には長時間労働が減っていても、
実際には「業務密度の高さ」や「心理的な圧迫感」がストレスの源になっています。
② 責任の重さと失敗への不安
2番目に多いのが「仕事の失敗や責任に関するストレス」。
特に管理職や中堅社員では、「部下を守る」「成果を出す」という両方のプレッシャーにさらされています。
上司と部下の間で板挟みになる“サンドイッチ現象”は、
メンタル不調の一因としても注目されています。
③ 仕事の質とスキルのミスマッチ
3位は「仕事の質(26.4%)」です。
これは「自分のスキルに合わない仕事を任される」「成長実感がない」といったケース。
キャリア開発が遅れることによる心理的停滞感も大きなストレスとなります。
ストレスの根本原因は「構造」にある
興味深いのは、強いストレスを感じる人が多い一方で、
法律上の「過重労働」に該当する人はごく少数という点です。
これは、ストレスが“時間”ではなく“構造”から生まれていることを意味します。
- 人手不足による仕事の集中
- 裁量の少なさ
- 不明確な評価制度
- コミュニケーション不足
こうした要因は、単に残業時間を減らすだけでは解決できません。
つまり、「見えないストレス」を組織的に減らす取り組みが求められているのです。
政策の転換点:「ストレスチェック制度」全事業所義務化へ
2015年に導入された「ストレスチェック制度」は、
これまで従業員50人以上の事業所のみ義務化されていました。
しかし2024年10月、厚生労働省はすべての事業所に義務付ける方針を決定。
これにより、中小企業や個人経営の職場も対象となります。
改正後の主なポイント
| 項目 | 現行制度 | 改正後(予定) |
|---|---|---|
| 対象 | 従業員50人以上 | すべての事業所 |
| 実施義務 | 努力義務 | 義務化 |
| 猶予期間 | なし | 公布から3年以内 |
| 目的 | メンタル不調の一次予防 | 全労働者の健康管理 |
この改正によって、約400万の小規模事業所が新たに制度対応を迫られることになります。
中小企業に求められる対応とは?
ストレスチェック制度の全事業所義務化は、
コンプライアンス面だけでなく経営課題として捉える必要があります。
● 現場で起こる課題
- 専門スタッフ(産業医・保健師)がいない
- 個人情報の管理体制が未整備
- 結果を活かした改善ができない
これらを補うために、中小企業では「外部EAP(従業員支援プログラム)」の導入が増えています。
ただし、EAP任せでは「制度をやっているだけ」で終わる可能性も。
集団分析の結果をどう改善行動につなげるかが鍵です。
集団分析の“やりっぱなし”から“活用”へ
ストレスチェックの本来の価値は、
個人のストレス状態を測るだけでなく、職場全体の傾向を可視化することにあります。
実際、調査によると:
- 集団分析の実施率:75.4%(前年比+6.2pt)
- 結果を活用した割合:76.8%(前年比−1.2pt)
つまり、多くの企業が「やることはやっている」ものの、
分析結果を活かしきれていない現状があります。
改善のためのポイント
- 結果を経営会議や衛生委員会で共有
- ストレス要因を定量化し、改善計画を立案
- 定期的にPDCAを回す
形式的な報告で終わらせず、人事戦略の一部として組み込むことが重要です。
キャリアとライフイベントに応じた支援の必要性
ストレスの原因は世代や立場によっても異なります。
| 層 | 主なストレッサー |
|---|---|
| 若手社員 | 成長プレッシャー・仕事の量 |
| 管理職 | 責任・人間関係(サンドイッチ現象) |
| 中高年層 | 介護・健康・将来不安 |
特に中高年層では、「仕事外のストレス(家族・健康・老後)」が増加傾向にあります。
企業は「仕事の負荷」だけでなく、ライフサポート制度の拡充も検討すべき段階に来ています。
まとめ:企業が今すぐ取り組むべき3つのステップ
仕事のストレスを軽減するためには、以下の3つの取り組みが欠かせません。
- 職場環境の見える化
ストレスチェックと集団分析で現状を把握 - 構造的課題へのアプローチ
「仕事量」「裁量」「人間関係」を中心に改善 - トップマネジメントの関与
形式ではなく“戦略的メンタルヘルスマネジメント”へ
ストレス対策は「従業員の健康を守ること」だけでなく、
離職防止・生産性向上・企業価値向上につながる経営戦略です。
Last Updated on 2025年10月9日 by ひらや